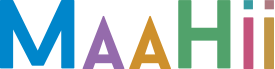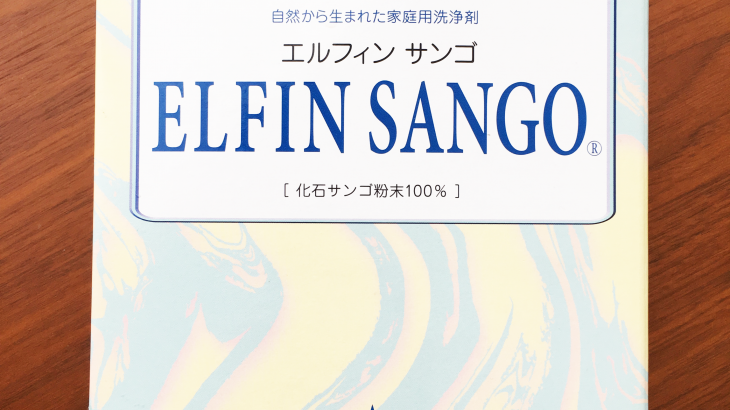公園で、無料の落ち葉堆肥を手に入れました。

しかし、その落ち葉堆肥の発酵が未熟だったんです。
葉っぱが十分に細かくなっておらず、ちょっとドブ臭い。
このままでは、堆肥として使えない。
なので、米ぬか、もみ殻、ヨモギ発酵液、「どなん」(化石サンゴ)を使って完熟発酵させることに。
今回は、未熟な落ち葉堆肥を、ヨモギ発酵液を使って完熟させる実践記録です。
未熟な落ち葉堆肥(腐葉土)を埋める穴を掘る

腐葉土は、木枠の中でつくるのが一般的

通気性が良い、木枠を使うのがベスト。
大型のポリ容器なども排水性、通気性を改善すれば代用できます。
今回は時間がなかったので、穴を掘って埋めることに。
未熟な落ち葉堆肥を完熟させるのに必要な物

今回の主役、未熟な落ち葉堆肥(45リットル×4袋)。
米ぬかともみ殻

堆肥は、目に見えない微生物の働きによって作られます。
なので、微生物をたくさん増やすことが完熟発酵へ近道。
米ぬかは、微生物の餌。
もみ殻は、通気性を良くします。
酸素が不足すると、微生物が死んでしまうので。
また、もみ殻は、微生物たちの住処にもなるそうな。
どちらも、北広島市タカシマファーム直売所「ふらり」で購入しました。
ヨモギ発酵液

「ヨモギ発酵液」とは
ヨモギの新芽と、黒砂糖のミネラルを取り込んだ酵素液。
この2つの材料を発酵させることにより乳酸菌が作られ、微生物が豊富になる!
ヨモギ発酵液の効果
・ボカシ肥料の発酵促進剤
・野菜の追肥
・病害虫予防
・土壌の微生物が増え、野菜がすくすく育つ
また、「ヨモギ発酵液」の中にいる植物性の微生物は炭酸ガスを吸って、酸素を出します。
この酸素によって、嫌気と好気のバランスが保たれ、発酵が促進されると思っている。

どなん(化石サンゴ)

「どなん」は与那国島の化石サンゴで、ミネラルを豊富に含みます。
「どなん」の効果
・土壌中の微生物育成促進
・保水、通気性、保肥の増大
・酸性土壌の矯正 などなど

「どなん」は、これからの農業を支える重要な存在だと思います。
詳細は、コーラルインターナショナルのHPにて。
いざ!未熟な落ち葉堆肥(腐葉土)を完熟へ!!
①未熟な落ち葉堆肥を穴に投入!

なるべく、日当たりが良い場所に埋めましょう。
一般的には、水をかけながら落ち葉を踏み固めます。
が、今回は水をかけないことに。
「ヨモギ発酵液」の水分があるのと、すでに落ち葉が湿っていたから。
「微生物が活動しやすい環境を保つ」
有機物の分解、発酵には適切な「酸素(空気)」と「水分」を保つことが最大のポイント。
「酸素」は、微生物が生きてくのに必要。
微生物が増え、活動しやすい「水分量」は50~60%といわれております。
②米ぬか、もみ殻、希釈した「ヨモギ発酵液」、「どなん」を投入!!

③上に乗っかり、ふみふみと踏み固める。
①~③の工程を繰り返す。

作業は完了。
あとは様子をみて、必要時はかき混ぜて空気を入れる。
本当は、上に雨よけのブルーシートをかける必要があります。
しかし、この時は忘れていました(無念)。
完熟発酵の作業から2週間後・・・
発酵すると70度とかの発酵熱が出て、土が暖かくなる。
モクモク煙りが出てたらどうしよ~
ニヤニヤしながら、様子を見に発酵現場にかけつけたが。
土は、全く暖かくなかった。

まだまだ時間が必要。
一般的に、腐葉土ができるまで6~12か月かかるそうです。
ちょっとでも発酵促進してる素振りが見れることを、期待しちゃいました。
ブルーシートをかけ忘れた(その間、雨が降った)コトや、気温が低い(札幌、6月の平均気温は16℃)コトも要因かしら。
経過観察を続けます。
それでは、今日も最後まで読んでくれて、ありがとうございました。